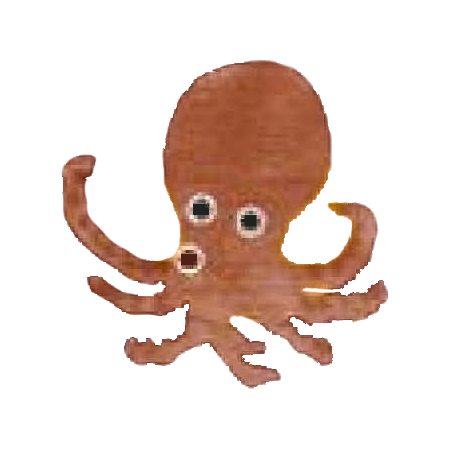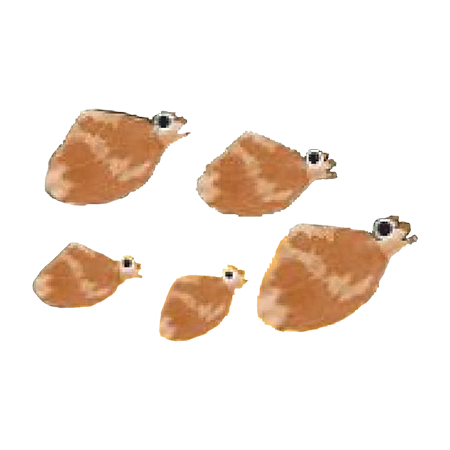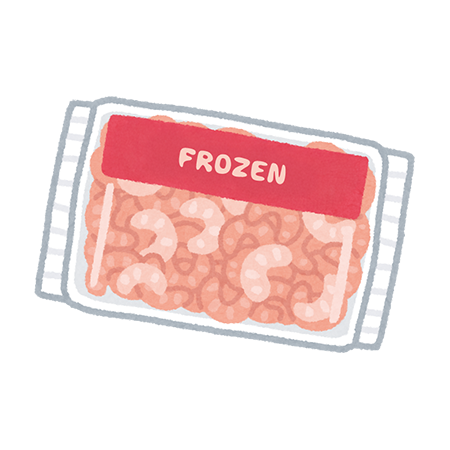取り扱い商材
エビ

赤しゃ(ザルエビ)・モギエビ
遠州灘より水揚げされた、正真正銘の赤しゃえびです。
水揚げ地である愛知県では、「赤しゃえび」「ザルえび」とも呼ばれています。
水深20m~100mに生息し、体長3cm~12cm。
車海老科のえびで、名前の通り、色が赤くよく出て甘味が強いのが特徴で、小さいけれどとても美味しいです。
煎餅の原材料には最高のもので、主に高級海老煎餅の原料になっています。
年間水揚げがありますが、最盛期は4月から9月くらいです。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

車えび
三河湾・伊勢湾・遠州灘にて水揚げがあります。
踊り食いは、車えびの天然ならではの甘さが際立ちます。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

白しゃ ざるえび
伊勢湾・三河湾からの水揚げが多く、年間水揚げがありますが、最盛期は4月から11月くらいです。
大きいものは大ザルと呼ばれ、茹でると赤くなり、頭の味噌と食べると大変美味しいです。
豊浜では赤しゃと呼ばれています。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

赤しゃ・キシエビ
主に伊勢湾・三河湾・遠州灘で水揚げされます。
あまり大きくならず、さるえびなどと共に水揚げされます。
これも赤色で甘味があり美味しいです。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

芝えび
主に伊勢湾で水揚げされます。
全国の水揚げ地は、東京湾・瀬戸内海・佐賀の有明が有名。
昔は東京・芝浦のあたりで多く水揚げがあり、この名前がついたそうです。
主に東京での寿司ネタやかき揚げに使われるために出荷されます。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

赤じん(ジンケンエビ)
主に遠州灘の深海にて水揚げがあります。
水揚げ地である愛知県では「赤じん」とも呼ばれています。
水深200m~350mに生息し、体長は5cm~10cm位。
角・ヒゲが長く、水分が多くて身が柔らかく甘いのが特徴で、海老煎餅の原料他、桜えびのようにかき揚げに使用されています。
最盛期は4月から6月。
7・8月は禁漁で9月からまた水揚げがあります。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

ひげ長エビ(ヒゲナガエビ)
主に遠州灘の深海にて水揚げがあります。
水揚げ地である愛知県では「ガスエビ」とも呼ばれています。
水深200m~600mに生息し、体長は15cm位。
身は柔らかく、殻は噛み切れる位で、甘みがあります。
海老煎餅の原料の他、惣菜(ムキ身は点心、天むす。殻つきのままオイル煮、唐揚げ等)に使用されています。
最盛期は4月から6月。
7・8月は禁漁で9月からまた水揚げがあります。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

トンガラシ(ツノナガチヒロエビ)
主に遠州灘の深海にて水揚げがあります。
水揚げ地である愛知県では、赤い見た目から「トンガラシ」とも呼ばれています。
水深200m~400mに生息し、体長は15cm位。
全体的にやわらかく、大型の割には可食部分は少なめです。
海老煎餅の原料の他、惣菜(殻付きのまま、オイル煮等)に使用されています。
目を引く色の為、素材を見せて調理するオープンキッチンの飲食店で使用されています。
最盛期は4月から6月。
7・8月は禁漁で9月からまた水揚げがあります。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|
タコ

真ダコ(本だこ)
低カロリーで、ビタミンB群、鉄、亜鉛、銅、カルシウムが豊富。
遠州灘や伊勢湾・三河湾にて水揚げされます。
大きいものは3~4kgぐらいになり、夏場は特に旨みが強いです。
明石のタコには負けません。
茹でたてにかぶりつくのが最高。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

水タコ
主に遠州灘の深海にて水揚げされます。
7・8月は禁漁期間。大きいものだと、5~6kgのものが水揚げされます。
柔らかくタコの旨みがよく分かる刺身・タコしゃぶ・タコ飯等大変美味しいです。
唐揚げも最高。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|
イカ

スルメイカ(真いか)
太平洋側・日本海側で水揚げされます。
三河湾で獲れるスルメイカは、標準的なスルメイカと比べて、必須脂肪酸であるDNAが約8倍。DHAは人の体でほとんど生成されない貴重な脂肪酸で、血液をサラサラにする効果が期待できます。タウリンも多く含まれているので、中性脂肪を減らし血液中のコレステロールを下げる働きもあります。
主に冷凍ですが、開イカ・下足などがあります。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|
あさり

三河湾のあさり
古来より、三河湾のあさりはその美味しさ絶品と称えられ、三河湾の海岸では春の風物詩として潮干狩りを多く見受けられます。
また漁獲高でも全国一位として愛知の特産品に挙げられています。
そこで当社では、そのおいしい三河湾のあさりを全国の皆様方にご提供できるよう日々努力しております。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|
魚

めひかり(アオメエソ)
主に遠州灘の深海にて水揚げがあります。
水揚げ地である愛知県での通称は「メヒカリ」。他地域では「トロボッチ」とも呼ばれています。
水深200m~300mに生息し、体長は15cm~20cm。
身がやわらかくふっくら脂ののった白身が特徴です。
メヒカリの唐揚げは、蒲郡市近隣でも郷土のメニューとして学校給食にも採用されています。
「大・中・小・小小」に分けてあります。
アミえびを食べていますので、魚自体にも脂が適度にあり、どんな風に調理してもおいしいです。
火を入れれば丸々食べられる栄養豊富な肴です。
年々漁獲高が減り、今では大衆魚から高級魚にランクアップしています。
最盛期は1月から6月。7・8月は禁漁で9月からまた水揚げがあります。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

ニギス
深海200m~300mに生息し、地域によっては「メギス」「沖ギス」とも呼ばれます。体長は20cm前後。例年7・8月は禁漁期です。
小ぶりな見た目からは想像がつかないほどふわふわとした食感の白身は、口の中でほろほろとほどけ、とろけるような脂ののりを感じます。
ワカサギに比べて脂のりの良さを示す脂質が約2倍あり、うま味成分であるイノシン酸も多く含まれます。
地元では、天ぷら・フライ・団子汁・塩焼きにして食べます。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

金目鯛
金目鯛は名前に「鯛」がつきますが、実は鯛の仲間ではなく深海魚です。
水深200m~800mに生息し、体長は30cm~50cm位。
白身魚ながら脂がよくのっており、トロリとしていて濃厚な旨みが魅力の高級魚です。
身はふっくらとしてやわらかく、小骨が少なく、子どもや高齢の方にも食べやすい魚です。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

黒ムツ
黒ムツは深海魚で、水揚げされる量が少ないので、市場では高値で取引される高級魚です。秋から冬が旬とされており、水深200m~500mに生息、体長は30cm~80cm位です。
大きく引き締まった白身からじわっとあふれる脂が、高級な口どけを与えてくれます。乳酸の代謝を促すアンセリン(ジペプチド)がマダイに比べて約3倍。抗酸化作用などの機能があることが知られています。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|

赤エイ
地元三河地域では、煮付けや唐揚げに餡をかけて食べています。
練り物の材料としても利用されています。フランスでは、皮を剥いてムニエルにして食べます。
アサリやシャコ等美味しい海の幸を捕食しています。骨が大きく可食部分は少ないですが、白身で繊維質な身は柔らかく、くせがありません。
鮮度が落ちるとアンモニア臭がしてしまうため、その日のうちに処理をしています。
眼精疲労、骨や免疫、肝機能を強化する他、皮膚の働きを改善する働きがあると言われており、細胞の老化を防いだり、関節炎を予防する作用もあります。豊富に含まれているコラーゲンには細胞と細胞を結合する作用があり、体の新陳代謝を活性化させる効果があります。
| 状態 |
|
|---|---|
| 調理方法 |
|
加工品
お弁当や酒の肴に!
メヒカリ唐揚げ
真ダコ唐揚げ
※この他にも様々な加工品を販売しております。